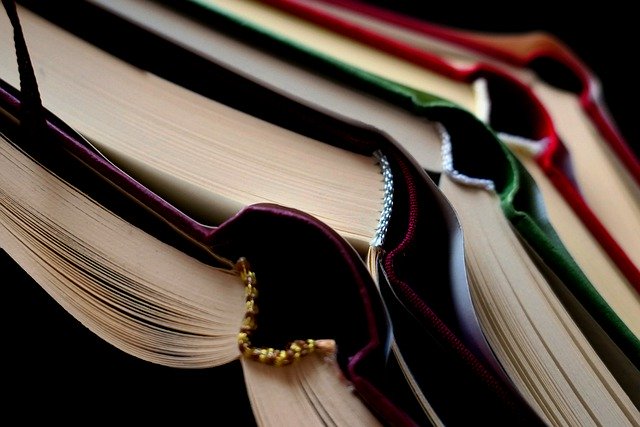院試勉強(内部・外部)はいつから始める?院試対策のポイントと合わせて解説!

大学受験の時は高校2年の終わりから、本格的に受験勉強しないといけない雰囲気になるので、否が応でも勉強モードに入れますよね。
しかし、院試は全員受ける訳ではないので、

院進学しようと思うけど、院試勉強っていつから始めるもんなの?

外部受験しようと思うけど、やっぱ早めに院試対策した方がいいの?
というように、いつから院試勉強を始めていいか分からないという人も多いはず。
今回は、院試勉強はいつ頃から始めるべきなのか、院試対策する際のポイントも合わせてご紹介します!
※この記事は3~4分で読めます
🕐2020年05月06日
目次
院試に関するよくある勘違い

本題に入る前に、一つ確認です。
そこのあなた、院試をナメていませんか?
院受験する学生の中には、間違った情報を鵜呑みにして、院試を甘く見ている人が見受けられます。
そこで、院試に関するよくある勘違いを3つ紹介しますので、もし当てはまったらその考えは今すぐ改めた方がいいでしょう。内部・外部関係なく落ちますよ?
1.院試の勉強は一か月あれば十分

俺、受験の一月前から院試勉強始めたけど、普通に受かったで(笑)
このような先輩の武勇伝を聞いて

そうなんだ!じゃぁ俺も直前に勉強すればいいや!
と思っていませんか?特に内部生の人。
院試、ナメんじゃねぇよ
院試は難易度も出題範囲も定期テストと全く違います。一か月ちょろっと勉強した程度で対策できるほど甘くありません。
点数を取れなければ、内部生でも容赦なく落とされます。
人気のある研究室なら間違いなく、内部と外部で席の取り合いになります。実際に外部生との競争に負けて、院浪人した内部生もいます。
院試勉強は1か月で大丈夫と思っているのなら、その考えは捨てましょう。
2.院試の問題は大学受験より簡単
ネットで良く見かけるのが
「院試は大学受験も問題よりも簡単だから、大学院は余裕で入れる」
という情報。
院試、ナメんじゃねぇよ
大抵こういう類のデマを振りまくのは
- ・実は院試を受けたことのないホラ吹き
- ・自分の頭の良さを自慢したい痛い奴
のどちらかです。
専門科目に関しては、高校時代とは比べ物にならないほど専門性が高くなっているので、大学受験より問題が簡単になるワケがないですよね。
院試に受かるボーダーラインはおおおそ6割と言われていますが、その6割を取るのが難しいのが院試です。
しっかりと腰を据えて勉強しないと、院試は到底突破できませんよ。
3.院試の点数が悪くてもコネがあれば受かる

うちの教授は京大の××教授と仲いいから、点数悪くてもコネで京大入れちゃうぜ!
なんて、思っている学生はまさかいませんよね?
院試、ナメんじゃねぇよ
コネで学歴ロンダできるとか、時代錯誤も甚だしいですね。昭和じゃないんですよ?
あと、菓子袋抱えて何回も研究室訪問したら教授に気に入ってもらえて、点数悪くても入れてくれるとか信じてませんよね?
昔はそれで通用したかもしれませんが、今は無理です。
院試の点数が良い順に希望する研究室に配属され、ボーダー以下は自動的に不合格です。
コネとか言ってないで、真面目に勉強しましょう。
院試スケジュールはしっかり確認しておこう

気が引き締まったところで、まずは院試のスケジュールについて確認しておきましょう。
大学受験と違って、意外とやらないといけないことが結構あります。
大学によって多少の違いはあるかもしれませんが、大体次のように院試は進められます。
- ・3月:研究室訪問(外部生)
- ・4~5月:研究科説明会
- ・6月:願書提出
- ・8月:筆記試験&面接試験
- ・9月:合格発表
研究室訪問は研究科説明会の時でも可能ですが、見学時間が決まっていて見学者も大勢いるので、詳しく質問したりする事は難しいです。
個人で研究室訪問しておくと、時間も十分あり聞きたい事を全部聞けるので、春休み期間中などに研究室訪問しておくことをおすすめします。
また、外部受験の場合、複数の大学を受験すると思うので、試験日が被らないようにスケジュール調整を行って下さい。
院試の勉強はいつから始めるべき?

それでは本題である、いつから院試勉強すればいいかを解説します。
内部受験と外部受験で違うので、別々に紹介します。
内部受験は遅くても試験3か月前から
内部生の場合
- ・過去問が十分に揃っている
- ・学部の講義で院試に必要な基礎学力が出来上がっている
- ・研究室の先輩にアドバイスをもらえる
といったアドバンテージがあるので、それほど早く始めなくても対策できることが多いです。(京大や東大の中でも難関の専攻は除く)
なので、遅くても試験の3か月前くらいから、始めるのがいいでしょう。スケジュール的には
- ・5月に基礎を復習
- ・6月に応用
- ・7月に過去問で演習
というように勉強すれば十分対策できるかと思います。
ただし、英語に自信が無い場合は、年明けからコツコツ勉強しておくことをオススメします。
外部受験は1年前から始めると余裕が持てる
外部受験の場合
- ・受験する大学院・専攻の決定
- ・研究室訪問
- ・説明会参加
- ・受験する大学院の過去問入手
というように、やるべきことがたくさんあります。
また、情報収集が大事になってくるので、院試の1年前くらいから準備を始めておくことをおすすめします。
遅くても学部3年の春休みには院試勉強を始めないと、恐らくスケジュール的にもカツカツになります。
今の大学より偏差値の高い大学院を受験するなら、春休みまでに基礎を完璧にして応用に入らないと、院試で太刀打ちできないので、勉強を始めるのは早いにこしたことはありません。
院試対策のポイント

卒業研究もしつつ、院試対策もしないといけないので、院試勉強は効率よく進めることが重要になります。
そこで最後に、院試勉強を効率よく進めるためのポイントを紹介します。
1.1人で勉強しない
大学受験ではよく「受験は団体戦」と言われますよね。
院試も同じで、1人より複数で勉強した方が効率が良いです。
- ・モチベーション維持
- ・院試情報・過去問の共有
- ・知識の抜けを補い合える
などのメリットがあります。
1人で勉強していると、気づかぬうちに間違った方向に進んで、取返しのつかないことになりかねません。
そのため、院試勉強する際は、院試受験の仲間を見つけて一緒に勉強することをおすすめします。
2.過去問は一年分でも多く確保する

大学受験の時は赤本を使って勉強していましたよね。
院試も過去問を使って勉強することは非常に大事です。問題の出題傾向も分かりますし、何より抜けている知識の確認にもなります。
そのため、過去問は1年分でも多く確保しておきましょう。
もし、どうしても数年分しか手に入らないのなら、他大学院の過去問を使って勉強するという手もあります。
知識をアウトプットすることが何より大事なので、気になる大学院の過去問は全てダウンロードしておいて損はないでしょう。
3.英語は早めに勉強を始めておく
院試は専門科目と英語が必ずセットです。TOEICで英語試験が免除される大学院もありますが、上位の大学院だと独自の英語試験がある場合が多いです。
ついつい専門科目ばかりに気を取られがちですが、英語の対策も忘れずにしておきましょう。
一朝一夕で身に付くものではないので、英語の対策は専門科目よりも早めに始めることをおすすめします。
院試の英語試験は各専攻に合わせた内容が出題されることが多いので、英語版のテキストやレビュー論文などを利用すれば、リーディング対策と専門英語の勉強にもなります。
4.内部生が授業で使っている教科書で勉強する
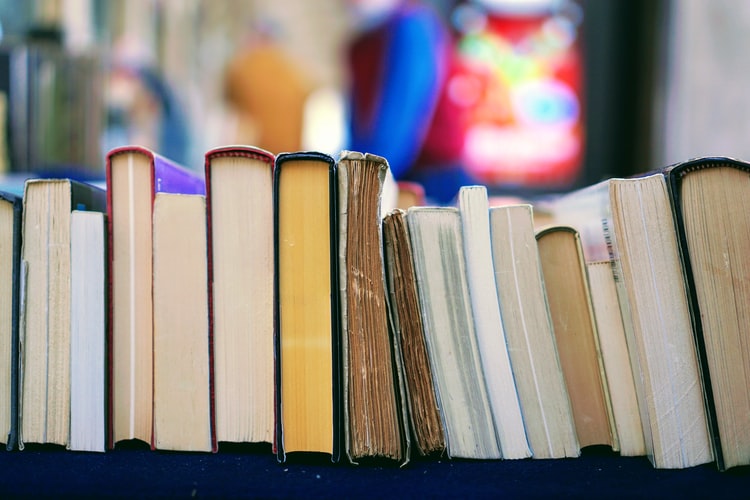
内部受験は関係ありませんが、外部受験する際は必ず、受験する大学で使われている教科書で勉強するようにしましょう。
といのも、院試も一応出題範囲というものが各大学院で決められており、学部の講義で使われている教科書を出題範囲としているところが多いからです。
教科書によって難易度や掲載内容が多少異なっているので、受験先の教科書で勉強するのが一番確実で効率がいいです。
もし、受験先の教科書が分からなければ、研究室訪問時などに聞いてみるといいでしょう。
5.面接対策は院試直前でも大丈夫
院試は筆記試験と一緒に面接も行われます。
正直、院試の面接は「人間として問題がないか」を見極めるものなので、就活ほど時間をかけて対策する必要はありません。
質問内容も大体決まっているので、試験の1,2週間前から勉強の合間に少しづつ対策すればいいでしょう。
院試の面接に関しては、次の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
まとめ
院試は世間一般で思われているほど簡単ではありません。
しっかり勉強しないと、内部生でも落ちる可能性大です。
外部生は特にハンデを負っているので、情報収集も含め、早めに対策を始めるようにしましょう。
研究室に入ってしまうと、腰を据えて座学の勉強をする時間も取れなくなるので、院試勉強でしっかり知識を付けて、良い大学院生活をスタートできるようにしておきましょう!
使わなくなった大学の教科書、売りませんか?
大学3、4年生にもなると、講義で必要だから買ったけど、もう2度と読まないような教科書があったりしませんか?
古本屋やフリマアプリで売れればいいですが、
- ・買いっ取ってもらえなかった
- ・出品しても全然売れない
- ・売れても数百円しか戻って来なかった
なんてこともありますよね。
でも、専門書アカデミーなら、どこよりも高値で買い取ってくれるかもしれませんよ?
専門書アカデミーは、大学の教科書や専門書、就職試験などの教材の買取に特化したサイト。
1点ごとに人気や需要を見て買取価格を査定し、人気の高いものは発行年度に関わらず高値で買い取ってくれます。
買取は宅配便の着払いで何箱でも全国送料無料、しかも希望の方には段ボールも無料でもらえちゃえます。
古本屋で売れなかった教科書も、専門書アカデミーなら高価買取してくれるかもしれません。
処分してしまう前に一度、買取査定に出してみませんか?
買取査定に出してみる